ハーブは私達のまわりに生えている草の中で、薬効があったり、
殺菌作用があったり、消化を助ける作用にすぐれていたり、なんらかの意味で人間に役に立ってきた香草です。

農場のチャイブ
ハーブは国または地方によって育つ種類も違い、人は身近かに生えている香草を上手に取り入れ、生命の維持に役立て暮らしを豊かにしてきました。北広島の農場に来たドイツの青年は、小さいときに喘息があり、’’ママが食事の時に必ずローズマリーティーを作ってくれて飲んでいました。今元気なのはそのおかげと思っています。ハーブは家では西洋の漢方薬なのです。’’と話していました。
日本でいえば山椒、よもぎ、しそ、せり、笹の葉、庭に沢山あったどくだみ等、料理に香や風味をつけるとともに腐敗を防いだり、消化を助けたり、煎じて家庭薬に使ったものもあります。
ハーブという名前がラテン語に由来する外国語のため、まったく新しい植物という意識の方も沢山いらっしゃいました。30年ほど前にはハーブという名前の植物と思われている方もいて、ハーブが総称ということすら知られていませんでした。
一時ハーブが流行になり、雑誌やテレビで取り上げられましたが、ハーブはおしゃれ!!高級なものという雰囲気が出来上がってしまいました。
釧路管内でハーブの講演をさせていただいた時、代表がご高齢の男性で1ヶ月一度、6ヶ月の講演でしたが一番最初は驚くほど関心がなく、悩みました。次の月は本来は次に進む予定でしたが、お願いをして再度(ハーブとは!!)というお話をすることにしました。
なぜ感心がなかったかというとその男性は‘‘俺は和食なのでそったら洋食なんか食わねぇ!!‘‘
とのことで日本のハーブの話をしたり、最後に行うハーブ料理も
‘‘やっぱり和食だべ~’’
ということでそこで獲れた鮭の香草焼き、ナスタチウムの花寿司、イワシの香草つみれ団子汁を作る事で6ヶ月のハーブ講座をスタートすることになりました。
料理に使う暮らしというより、おしゃれに飲むハーブティーだったりポプリだったりと暮らしというより嗜好品となったことがハーブを使う料理というだけで毛嫌いされたのだとその時思いました。
この数年はようやく本来のハーブの良さを理解していただけた方も多くなり、園芸店でハーブの苗が必ず扱われ、庭にもハーブが普通に植えられるようになりました。
ハーブを育てる人も増えてきて、ハーブを料理に使う人も多くなってきてこんな質問もでるようになりました。’’園芸店でハーブの苗を買って植
えましたが食べられますか?’’
園芸ブームに乗り沢山の種類のハーブが出回っています。今まで料理に使ったことのないハーブが出回り、ハーブと名がつくとすべて食べられると思う人も多くいます。視覚優先に花を観賞しようと、品種改良をした園芸種も多くあり、食用に向かないハーブも少なくありません。
近年パクチがブームとなり、お野菜のように使われるようになりました。アメリカではデザイナーズフーズといわれているアメリカ国立がん研究所作成のデーターでもがん予防になる野菜40種のなかににんにくを筆頭にバジル・ハッカ・オレガノ・タイム・セイジ等色々なハーブが含まれています。
北広島の農場でもパクチを生産しています。昨年は毎週1kgづつ買いに来てくれた女性もいて、パクチの根の素揚げの作り方をお話した
ら‘‘、美味しくてはまっています。‘‘ との事でした。
昔からある伝統的なハーブを日常の料理にどんどん使って貰いたい!!一人でも多くの方がハーブの魅力を知ってハーブと共に暮らしていけたなら!!と心から願っています。
そんな思いで日々スタッフとハーブな絨毯・ハーブなお茶・ハーブな野菜を育てています。



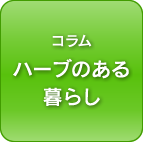







 う
う




















